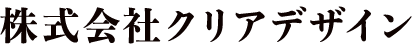投資用物件を建てる際、「長屋」と「共同住宅」のどちらを選ぶべきか悩むオーナー様は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、共同住宅の方が投資効率が高い傾向にあります。
投資効率を最大化するためには、それぞれの特性を正しく理解し、メリット・デメリットを比較することが重要です。
本記事では、長屋と共同住宅の定義の違いから投資視点でのメリット・デメリット、さらに投資効率の観点での比較まで徹底的に解説します。
共同住宅の方が投資効率が高いといえる理由も解説しますので、これから投資用物件の建設をお考えの方はぜひ最後までお読みください。
なお本記事は、狭小地での投資用物件の設計に豊富な経験をもつ一級建築士の監修のもとお届けしています。

【監修者】
株式会社クリアデザイン
代表取締役
一級建築士 佐藤 洋輔
オーナー様の夢を形にする建築パートナーとして
店舗工事の企画・設計・施工・コンサルティングや
投資用物件の内装・外装工事の企画・設計・施工を一貫して行っております。
長屋・共同住宅の定義の違い
まずは、長屋と共同住宅の基本的な違いを明確にしておきましょう。
長屋とは
長屋とは、横に連続した住戸が一つの建物として繋がっている形式の住宅を指します。
各住戸に直接外部から出入りでき、エントランスホールや共用階段などの共用部分がないのが特徴です。
戸建てと集合住宅の中間的な位置づけと考えられます。
共同住宅とは
共同住宅とは、アパートやマンションのように複数の住戸が上下左右に配置された形式の住宅を指します。
他の住人同士で利用する共用の廊下や階段、エントランスなどの共用部分を備えているのが特徴です。
長屋・共同住宅の投資視点でのメリット
投資用物件としての長屋と共同住宅には、それぞれ独自のメリットがあります。
長屋のメリット
長屋のメリットは以下のとおりです。
1.路地状敷地(旗竿地)でも建てられる
長屋の最大のメリットは、旗竿地や間口の狭い敷地でも建設が可能な点です。特に、土地の坪単価が比較的安い旗竿地を有効活用できることが大きな魅力です。
2.共用部分のコストが抑えられる
長屋には共用部分がないため、エレベーターや廊下などの建築費用を削減できます。
ただし、上階がある場合は各住戸内に階段を設置する必要があるため、その分建設コストが上昇する点には注意が必要です。
3.管理コストが低い
長屋は入居者が比較的少ないため、トラブル対応や契約管理の手間が少なく、管理コストを抑えやすいです。
また、共用部分が少ないことで清掃やメンテナンス費用が軽減されるため、初めての投資にも取り組みやすい物件タイプといえます。
共同住宅のメリット
以下、共同住宅のメリットです。
1.土地利用効率が高い
共同住宅は、階数を増やすことで同じ敷地面積でも多くの住戸を配置できるのが最大のメリットです。
この特性により、限られた土地を有効活用できるため、長期的な安定収益が見込めます。
2.幅広い賃貸需要に対応可能
共同住宅は、その立地やターゲット層に合わせて、単身者向けの1Kからファミリー向けの3LDKまで、多様なニーズに応えられます。
特に都市部では共同住宅の需要が高く、空室リスクが低い傾向にあります。
3.資産価値が高い
共同住宅は土地の利用効率が高いため、資産価値が安定しやすい点が特徴です。
また、市場での流通性が高く、売却時には有利な条件で取引されることが多いです。
立地によっては、将来的な資産価値の上昇も期待できる場合もあります。
長屋・共同住宅の投資視点でのデメリット
一方、それぞれに注意すべきデメリットもあります。
長屋のデメリット

まず、長屋のメリットは以下のとおりです。
1.土地利用効率が低い
長屋は横に広がる構造のため、高さを活用して住戸数を増やせる共同住宅と比べると土地の利用効率が低くなります。
また、旗竿地に長屋を建てた場合、建て替えの際に制限がかかることも大きなデメリットです。
旗竿地では戸建てか長屋しか建てられないため、土地の利用用途が限られ、土地価格が比較的低くなる傾向にあります。
2.収益性が限定的
長屋は各住戸の賃料が比較的低く設定されることが多く、その結果、総収益が限定されやすい傾向があります。
よって、他の投資物件と比べて安定した収益を得るのが難しい場合があります。
3.需要が限定的
長屋は主にファミリー層をターゲットとして設計されるため、単身者や高齢者向けには適しません。
そのため、多様な入居者層をターゲットにできる共同住宅と比べると、賃貸市場での競争力が劣る可能性があります。
共同住宅のデメリット

次に、共同住宅のデメリットは以下のとおりです。
1.日影規制や耐火建築で高さに制限がある
共同住宅は、高さを活用して住戸数を増やせるものの、建築基準法により、階数を増やすには高さの規制やコストの壁があります。
具体的には、都心部のような住宅密集地では高さを10m以内に抑えなければいけない「日影規制」や、4階建て以上は耐火性能の確保が必要なことなどです。
そのため、日影規制をクリアしながら4階建ての実現や、耐火建築物でありながらコストを抑えて4階建てを実現する方法を積極的に取り入れることが重要です。
詳しくは、「狭小地で収益性をあげるための4つの工法をご紹介!」の記事をご覧ください。
2.管理が複雑
共同住宅では、入居者が多い分、トラブル対応や契約管理などの業務が複雑になる場合があります。
そのため、外部の管理会社に業務を委託するケースが一般的です。
これにより管理負担は軽減されますが、追加のコストがかかります。
3.維持費がかかる
共同住宅では、共用部分(階段や廊下など)の清掃や設備の定期的なメンテナンスが必要です。
これらの維持費が運用コストとして発生するため、それらを考慮した収支プランで考える必要があります。
長屋・共同住宅の投資効率での比較
ここからは、長屋と共同住宅の投資効率について、以下の項目で比較して解説します。
1. 土地利用効率
長屋は横方向に広がる構造のため、土地利用効率が低くなる傾向があります。
一方で、共同住宅は高さを活用することで、同じ土地面積でも多くの住戸を配置でき、土地の有効活用が可能です。
このため、特に都市部のような土地が限られる地域では共同住宅が優位といえます。
2. 賃料収入
長屋は各住戸の賃料が比較的低めに設定される場合が多く、収益性が限定される傾向にあります。
これに対して、共同住宅は複数の住戸から安定した賃料収入を得られるため、長期的な収益性が高い点が魅力です。
また、単身者向けからファミリー向けまで幅広いニーズに応えられる点でも、共同住宅の方がより収益性が高いといえるでしょう。
3. 維持管理
長屋は共用部分がないため、清掃や設備のメンテナンスにかかる費用を抑えられるのが大きな特徴です。
一方、共同住宅は階段や廊下など共用部分が多いため、維持管理費用が増える傾向があります。
ただし、外部の管理会社に一括して管理業務を委託することで、運営効率を高めることが可能です。
また、管理コストをかけること自体は、必ずしもマイナス要素とは言えず、適切な管理によって物件の資産価値を維持しやすくなるというメリットもあります。
4. 資産価値と融資
共同住宅は高収益を期待できるため、金融機関からの融資を受けやすく、資産価値も高い傾向にあります。
これにより、将来的な売却時にも高いリターンが見込めます。
一方、長屋は土地の評価が主軸となるため、活用幅が限られている旗竿地での評価額は限定的です。また、融資条件が厳しくなる場合があります。
共同住宅の収益性をさらに上げるならクリアデザイン

東京都渋谷区に拠点をもつ株式会社クリアデザインでは、お客様の土地の形や立地に最適な工法・設計方法で、収益性を考慮した設計デザインをご提供しております。
以下のような特殊工法で、その土地に合った収益最大化をご提案いたします。
- 細長い土地を最大限活用できる無足場での設計
- 日影規制をクリアした4階建てアパート
- コストを抑えた耐火構造の4階建てアパート
- 木造3階建てロフト付きアパート
投資用物件の建設をご検討中のオーナー様は、ぜひ一度、クリアデザインにご相談ください。
まとめ|土地効率と資産価値の高い共同住宅がおすすめ!
本記事では、長屋と共同住宅の定義の違いから、投資効率の比較まで解説しました。
長屋と共同住宅のメリット・デメリットを比較した結果、投資効率の観点では共同住宅が優位であることが明らかです。
- 土地利用効率: 高さを活用できる共同住宅は、限られた土地を最大限に活かせられます。
- 収益性: 住戸数を増やし、幅広いニーズに対応できる共同住宅は、安定した賃料収入が見込めます。
- 資産価値: 高収益を生み出す共同住宅は、融資条件や売却時のリターンでも有利です。
一方、長屋は旗竿地や間口の狭い土地での活用に適しており、初期費用や管理コストを抑えられる点が魅力です。ただし、近年では旗竿地の価格も上昇しており、長屋のメリットが薄れつつあります。
そのため、特に都市部や収益性を重視する場合は、共同住宅の方が投資効率が高い選択肢となります。
投資用物件を検討する際には、それぞれの特性を踏まえた上で、目標や土地条件に最適な選択をすることが重要です。
都心部の狭小地や細長い土地に「収益性の高い投資用物件」を建てたいとお考えのオーナー様、ぜひお気軽にクリアデザインまでお問い合わせください。